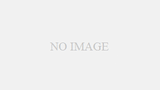①国内以外にも国際的な活躍が期待される企業
朋和産業株式会社と言うと、パッケージ関連の製品を製造し販売している会社です。
レンゴーグループに属する会社の1つですが、レンゴーグループの中で軟包装に関連する事業の中核をなす企業としての働きがあります。
このグループは、とても大規模で日本国内だけではなく外国にも事業を展開しているというのが特徴です。
包装に関連する業種は競合他社がたくさんあり激しい競争が展開されていますが、この会社はグループ会社の総合的な対応力を活かすことにより優位性を発揮しています。
そして、このグループ会社は紙の製造に関連する会社や紙で出来た器や段ボールを取り扱っている会社が数十社あるのです。
また、それ以外の分野の会社の関連会社や子会社も展開しています。
ちなみに朋和産業株式会社は軟包装に関連する事業に取り組んでいますが、このグループ会社の中には石油化学製品や飼料などを包装する重包装を取り扱う企業もあるのです。
このグループに属している会社は、グループの総合力を上手に活かしています。
特定の会社だけで、この競争社会を生き抜くのは大変ですがグループの中に入っていると色々支え合うことが可能ですし様々なメリットを受けることが可能です。
グループ会社としての社会的な地位を認知するには、外国での活躍に注目することが非常に重要になります。
中国やベトナム、タイやマレーシアなどのアジア諸国やアメリカにも関連会社や子会社を設けているため日本だけ留まらず国際的な活躍を期待することが可能です。
それぞれのグループに属している会社が扱う商品は異なりますが、大まかに分類すると同じものになります。
包装系統の事業を行っているのでノウハウを構築しやすい上に、関係性を効果的に活かすことにより規模が大きい取引に繋げることが可能です。
②地球環境に配慮した事業運営
朋和産業株式会社や他のグループ内の会社が優れた実績を積み重ねることが可能なのは、グループ会社の組織力によるものと言えます。
自分の会社のことしか考えていないのではなく、お客様になる可能性がある方たちや社会全体のことも充分に配慮しているのです。
公式ホームページに基本環境理念について掲載しているページが用意されているからも理解出来ますが、地球環境を保全することに配した事業運営を行っているのです。
近頃は地球環境を世界全体で保全しようとするムーブメントがありますが基本環境理念を実際に掲げて、その理念に基づいて事業を行っている会社は多くありません。
そのため朋和産業株式会社の行っていることが、どれだけ素晴らしいことかが理解出来るのです。
この会社では大まかに分類して方針を5つ設定していて、地球環境に気を配って事業に取り組んでいます。
このことは簡単なことようで、実現させるのは非常に困難です。
省エネルギーの具体的な目標値を設定していることも好ましいことですし、省資源化を行っていることも素晴らしいと言えます。
電子化を推進し紙を必要な分しか利用しない、ペーパーレス化も行っているのです。
環境を保全する活動に取り組むために必要となる体制を整えていることも、朋和産業株式会社の良いところになります。
会社の中に環境をマネージメントするシステムを構築していることも良いところの1つです。
目標を設定する上にマネージメントレビューを行う機会も設定することで、進捗状況を確認する体制も整っています。
他にも環境を保全するための色々な活動を行い貢献しているだけではなく、必要ならば環境に関する情報を提供しているのです。
・参考記事・・・朋和産業がFSC®認証範囲を拡大
③安心できる一貫した生産体制
法律や条例を守るという当然のことも徹底しており、広報活動にも注力しています。
会社の中には自分の会社の売上を増やすことだけに夢中になり、環境の保全や改善に関心がない会社も少なくありません。
そのような状況の中でも朋和産業株式会社は地球全体のことに関しても、ちゃんと気を配っているのです。
例えば、習志野工場に森を作り緑化活動を行っています。
環境ISO14001を取得しているのですが、この登録証は公式サイトにちゃんと掲載されているのです。
環境を保全することに注力している会社は、本業も手を抜かないため非常に信用することが出来ます。
自社のことしか考えないのではなく、社会全体のことにも配慮することが出来るので環境保全も本業も注目されているのです。
この会社では、安心することが出来る一貫した生産体制が整っています。
設計から製造、管理に至るまで一貫して取り組んでもらえるためプロセスを移行するときに欠陥が発生しにくいメリットを得ることが可能です。
設計と製造をそれぞれ別々の企業に依頼している人は、この会社にまとめて依頼するのが良い方法になります。
プレゼンテーションでは、パッケージの素材やデザインについての提案がされるのです。
次にデザインのデータが作成され、製版データが作成されます。
そのような過程を経て作成されたデータをベースにして、製版される訳です。